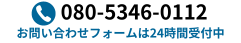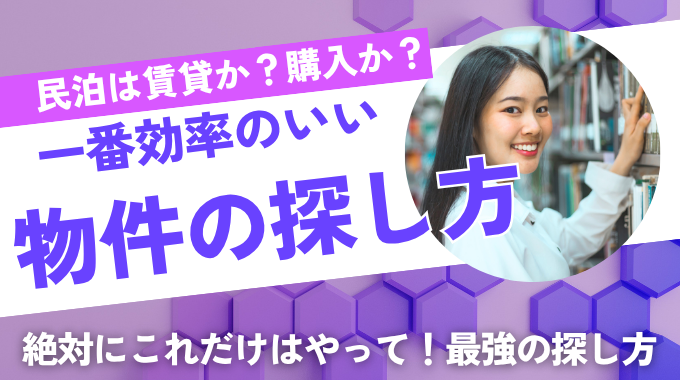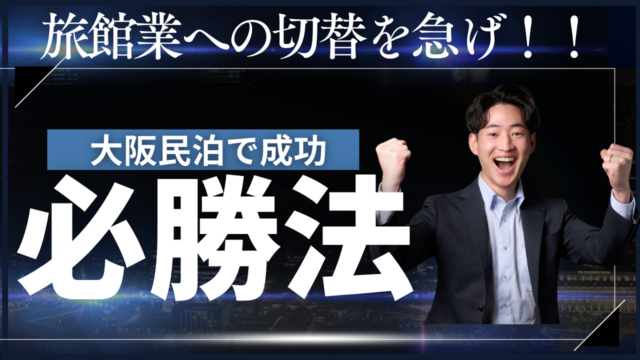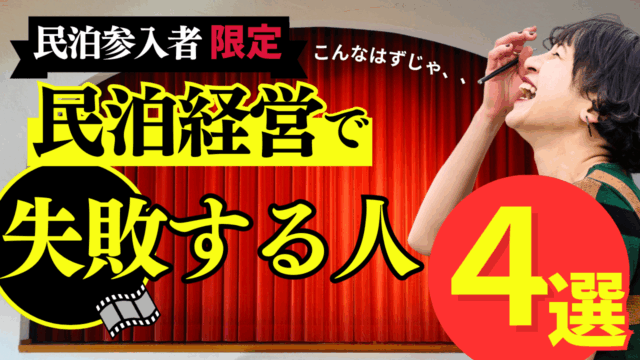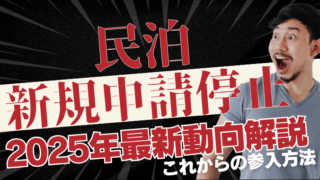「民泊可能な物件がなかなか見つからない…」と感じていませんか?
物件探しの難しさは、法規制や地域ルール、オーナーの理解不足など複数の要因が絡んでいます。賢く物件を選び、スムーズに運営を始めるためには正しい知識と戦略が不可欠です。
- 民泊事業をこれから始めたいが、物件探しで苦戦している方
- 2025年以降の注目エリアや物件選定のポイントを押さえたい方
- 専門家のサポートを活用しつつ、効率的に民泊物件を見つけたい方
なぜ民泊可能な物件がなかなか見つからないのか?

1.表面上は貸し出しOKでも「民泊不可」の落とし穴
不動産情報サイトなどで「短期貸し可能」「用途自由」などと書かれていても、実際には民泊としての利用が禁止されているケースが多く見られます。
これは、建物の管理規約や契約条件、オーナーの意向によって民泊営業が制限されているためです。特にマンションなどの集合住宅では、住民トラブルを防ぐために民泊禁止とする管理規約が設定されていることが少なくありません。
一見して可能に見える物件でも、管理会社に確認を取った結果NGになることは日常茶飯事です。
したがって、物件情報をうのみにせず、契約前に民泊利用の可否を明確に確認することが極めて重要です。
2.オーナーの理解不足・不安がネックになる背景
民泊を認めないオーナーの多くは、「トラブルになるのでは」「近隣住民から苦情が来るのでは」という不安を抱えています。これは過去に起きた迷惑行為やマナー違反などが報道などで広まり、民泊に対する印象が悪くなってしまっていることも一因です。
さらに、民泊は「商売」としての側面があるため、オーナー側が事業目的での利用に慎重になっているケースもあります。
3.仲介業者が積極的に紹介しない理由とは
不動産仲介業者が民泊可の物件をなかなか紹介してくれない背景には、「トラブルのリスクを避けたい」という心理が強く影響しています。
民泊運営には法律・条例・近隣配慮など複雑な知識が必要であり、業者側にとっても「関わりたくない案件」となってしまっていることがあります。
また、民泊運営者が入居後にトラブルを起こすと、物件オーナーからの信頼を失い、以後の取引にも悪影響が及ぶため、仲介業者自身がリスクを取らない選択をしているのです。
見落としがちな法規制と地域ルールの壁

1.「用途地域」と「建築基準法」の制限
民泊可能な物件であるかどうかは、建物そのものだけでなく、その物件がある「用途地域」や「建築基準法の制限」に大きく影響されます。
たとえば、住居専用地域ではそもそも旅館業の許可が出せない場合があり、住宅宿泊事業(いわゆる民泊新法)しか選択肢がないといったケースもあります。
また、建物の構造や階層、耐火性、避難経路の確保など、建築基準法の観点から営業に適していない物件も少なくありません。
2.特区民泊・住宅宿泊事業法・旅館業法の違いと物件選びへの影響
民泊には大きく分けて、「特区民泊」「住宅宿泊事業法(民泊新法)」「旅館業法」による運営形態があります。
それぞれの制度によって必要な設備や滞在日数の制限、営業可能な地域が異なるため、どの制度で運営するかによって物件選びの基準も変わります。
たとえば、特区民泊では2泊3日以上の滞在が義務づけられている一方、住宅宿泊事業法では年間180日までの営業制限があるなど、制度による営業条件の違いが戦略に大きく関わってきます。
この違いを理解せずに物件を選ぶと、許可が下りなかったり、営業制限の中で赤字経営になるリスクがあります。物件探しの段階で、運営予定の制度を明確に決めておくことが重要です。
3.地域住民とのトラブル回避のための独自ルール
地方自治体や管理組合が、独自に民泊に関するガイドラインや運営制限を設けている場合があります。たとえ法律上は問題なくても、地域の「協定」や「申し合わせ」によって、実質的に営業が難しいケースもあります。
特に、戸建て民泊やマンションタイプでの営業では、ご近所との関係性が非常に大切です。トラブルが起きれば営業停止やクレームに発展し、他の物件取得にも悪影響を与えかねます。
民泊可能物件の探し方を間違えていませんか?

1.一般の不動産ポータルサイトが向いていない理由
SUUMOやHOME’Sなどの大手不動産ポータルは、住居としての物件情報が中心であり、民泊目的での物件利用については記載されていない、あるいは禁止されていることがほとんどです。
そのため、表向きには魅力的に見える物件であっても、問い合わせをすると民泊不可とされてしまうケースが非常に多いです。
一般のポータルサイトはあくまで「住居」用途が前提であることを理解し、民泊用途に合った物件を探す際は、別の手段を取るべきです。
2.民泊対応の専門業者・管理会社の活用法
現在では、民泊に特化した物件紹介や運営代行を行う専門業者が増えてきています。
これらの会社は、法規制や地域特性に詳しく、オーナーとの交渉実績も豊富なため、最初から民泊可能な物件だけを紹介してくれる利点があります。
また、許可取得や設備設置などのプロセスも一括でサポートしてくれるため、初めて民泊に取り組む人でも安心です。
効率的かつ確実に物件を探すためには、こうした専門業者との連携が非常に有効です。
3.既存オーナーとの交渉ルートを開拓する
物件の選択肢が限られているからこそ、「交渉の余地があるオーナー」を見つけることが成功への近道になります。
民泊に理解のあるオーナーや、空き家の利活用に関心のある方であれば、条件次第でOKを出してくれるケースもあります。
直接交渉が難しい場合は、地域の不動産ネットワークや士業(行政書士・司法書士等)を通じてつながる手段も有効です。
「紹介ルートを作る」ことが、表に出てこない掘り出し物件と出会うカギとなります。
賃貸か購入か?成功者が選んでいる物件取得戦略

1.初期費用・リスク・自由度から見る賃貸のメリット・デメリット
民泊物件を賃貸で借りる場合、初期費用が比較的抑えられるのが大きなメリットです。自己資金が少なくても始めやすいため、初めての民泊運営には適しています。
しかし、賃貸は物件オーナーの意向に左右されやすく、民泊利用が禁止されたり、更新ができなかったりするリスクもあります。
また、契約条件によっては内装の自由度が制限され、思うような改装ができないことも珍しくありません。
一方で、物件の管理費や修繕費がオーナー負担である場合が多く、経費面での負担軽減にもつながります。
2.長期運用・自由度の高さから見る購入戦略
物件を購入する場合は、自由に内装工事や設備導入が可能で、物件の資産価値を自らの意思で高められます。長期的な視点で安定した運営を目指すなら、購入が優位な選択肢です。
ただし、初期投資は大きく、ローンの返済や固定資産税などの負担も発生します。
加えて、購入物件は市場流動性が低い場合もあり、転売時に思うような価格で売れないリスクもあります。
そのため、資金計画や運営計画を慎重に立てることが不可欠です。成功者の多くは、物件の立地や需要、法規制を綿密に調査した上で購入を決断しています。
3.サブリース物件という第三の選択肢
近年注目されているのが、物件オーナーから賃借して民泊運営を行うサブリース方式です。サブリースは賃貸と購入の中間的な立場で、運営の自由度とリスクのバランスが取れているのが特徴です。
契約形態や運営条件は業者によって異なりますが、管理業務や清掃、集客支援を一括で任せられる場合も多く、初心者にも始めやすい形態といえます。
ただし、収益の一部を運営会社に支払うため利益率は下がることが多く、契約内容をよく確認した上で検討する必要があります。
2025年以降に注目されるエリアと選定基準

1.観光需要とインバウンド回復による有望エリア
新型コロナウイルスの影響から回復しつつある今、インバウンド観光客の増加が見込まれる地域に注目が集まっています。
特に関西圏や大都市圏の観光名所周辺は、外国人旅行者の宿泊需要が高まっており、民泊物件の確保が急務です。
これらのエリアは、アクセスの良さや観光スポットの充実度から安定した集客が期待できる一方で、競争も激しく物件価格や賃料も高騰しやすい傾向があります。
需要と供給のバランスを見極めながら、慎重に物件を選ぶ必要があります。
2.空き家率の高い地域を狙った地方戦略
地方の空き家問題に目を向ける動きもあります。
空き家の多い地域では物件価格が安価で、自治体も空き家の利活用を推進していることが多いため、民泊事業者にとっては新しいチャンスとなっています。
地方では大都市ほどの集客は期待しにくいですが、自然観光や地方独自の体験を提供することで差別化が可能です。加えて、地域コミュニティとの協力関係を築きやすいというメリットもあります。
3.許可が取りやすい自治体の見極め方
民泊運営においては、許可や届出がスムーズに進む自治体を選ぶことが重要なポイントです。地域によっては、積極的に民泊誘致を行い、申請手続きのサポート体制が充実しているところもあります。
逆に、規制が厳しく許可が下りにくい地域では、運営開始が遅れたり、営業日数の制限が厳しい場合があります。
このため、物件選定前に自治体の担当部署とコンタクトを取り、最新の運営ルールや申請手順を把握しておくことが成功の鍵です。
まとめ

1.今後の物件供給と競争の関係
民泊物件は確かに探しにくくなっていますが、それは逆に市場が成熟しつつある証拠であり、適切な戦略を持つ事業者にとっては大きなチャンスでもあります。物件を押さえられれば、競合に差をつけやすくなります。
今後は民泊の許可基準や地域ルールも進化していくため、タイミング良く動くことが勝敗を分けるでしょう。
2.専門家への相談やサポート活用のすすめ
物件探しや許認可の手続きは複雑で専門性が高いため、早い段階で行政書士や不動産の専門家、民泊運営会社に相談することが失敗回避につながります。
彼らのネットワークやノウハウを活用することで、表に出てこない掘り出し物件や最新情報を手に入れることができ、円滑に準備を進められます。
3.「探す」ではなく「作る」民泊物件という発想の転換
最後に重要なのは、「物件を探す」ことに固執せず、「民泊可能な環境を自ら作る」という発想にシフトすることです。
空き家を購入してリノベーションする、オーナーと直接交渉して条件を引き出す、サブリース物件を活用するなど、多角的なアプローチでチャンスを広げることが成功への近道となります。